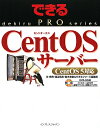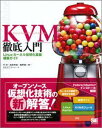(この文書は未完成)
RHEL 標準のクラスタソフトである、RedHat Cluster Suite(RHCS)を使って、Active-StandbyなOracleクラスタサーバを構築する。
CentOSでもほとんど同じ手順でクラスタ構築が可能。
Table of Contents
=================
1 参考ドキュメント
2 作業の流れと進捗チェックリスト
3 事前準備
3.1 IPアドレスの決定
3.2 ストレージパラメータの決定
3.3 Oracleパラメータの決定
4 RedHat Enterprise Linuxの設定
4.1 OSインストール
4.2 最新パッチの適用
4.3 ネットワークの二重化
4.3.1 /etc/modprobe.conf
4.3.2 ifcfg-eth0
4.3.3 ifcfg-eth1
4.3.4 ifcfg-bond0
5 共有ストレージの設定
5.1 RAID/LUNの作成
5.2 ホストへのマッピング設定
5.2.1 もし二つのノードからのデバイスの見え方が違ったら
5.2.1.1 ストレージの場合
5.2.1.2 ネットワークの場合
5.3 ストレージの結線
5.4 ストレージパスの二重化
5.5 ファイルシステムの作成
5.5.1 iSCSIをマウントする例
5.5.2 認識確認
5.5.3 ファイルシステムの作成
5.6 両ノードからのマウント確認
5.6.1 rhcs-oracle1から
5.6.2 rhcs-oracle2から
6 RHCSの基本設定
6.1 クラスタ化されるノードの設定
6.1.1 yum が使えない場合。
6.2 クラスタ管理サーバを設定
6.2.1 yum が使えない場合
6.2.2 管理画面へのアクセス
6.3 クラスタノードを管理サーバへ参加
------------------------------------- ここで力尽きてる
6.4 Fencingの設定
6.5 Quorumディスクの設定
7 RHCSのリソースとグループの設定
7.1 リソース 仮想IPの設定
7.2 リソース 共有ディスクの設定
7.3 グループ 依存関係の定義
7.4 グループ 起動と停止の確認
8 単体SPFテスト
8.1 OS起動・停止
8.2 手動フェイルオーバー
8.3 手動フェイルバック
8.4 ネットワーク切断
8.5 ストレージパス切断
9 Oracle設定
9.1 インストール
9.2 パッチ適用
9.3 データベースの作成
9.4 リスナーの作成
9.5 起動・停止スクリプトの作成
9.6 設定ファイルを両ノードのコピー
9.7 両ノードでデータベースとリスナーが起動する事を確認
10 RHCSへのOracle組込み
10.1 Oracleリソースの作成
10.2 依存関係の定義
10.3 起動・停止・フェイルオーバーテスト
11 結合SPFテスト
11.1 ネットワーク障害
11.2 ストレージ障害
11.3 OS障害
11.4 データベース障害
11.5 リスナー障害